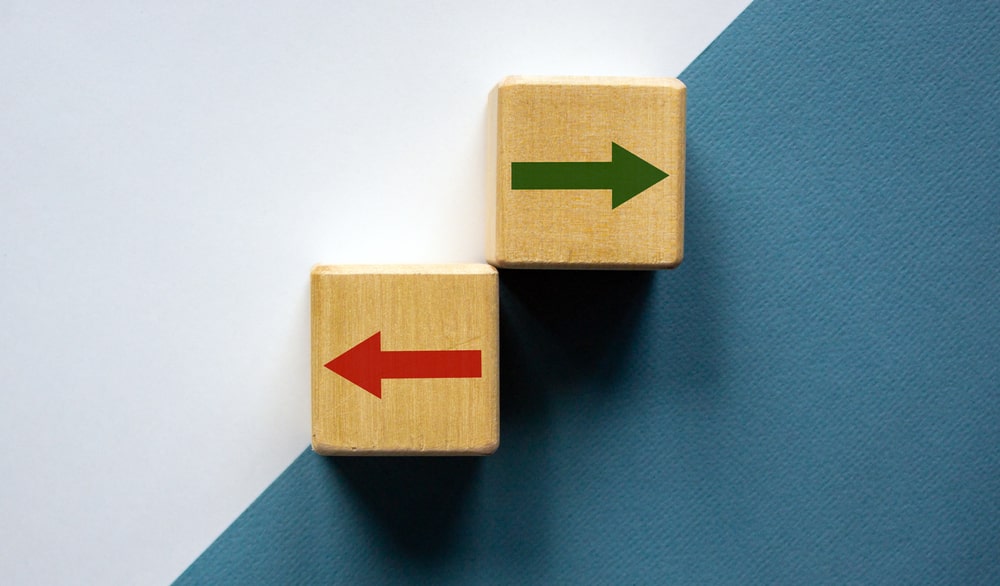永代供養塔って何?意味や特徴、費用相場について解説!

人口が都市部に集中するとともに、地方にある先祖代々の墓を墓じまいする人が増えています。墓を整理した後、遺骨は寺院や霊園内に合祀・合葬されることがあります。そうした場所に建てられているのが永代供養塔です。今回は供養塔の意味や形をはじめ、永代供養を利用するメリットなどについて解説します。
そもそも供養塔とは
供養塔とは、亡くなった人の霊を慰めるために建てられた石造りの塔のことです。供養という言葉は仏教の用語で、仏や菩薩、諸天などに供物を献上することを意味していました。
のちには、亡くなった人に供物を捧げることや、死者の冥福を祈るための追善なども一般的に行われるようになります。その歴史は平安時代の末までさかのぼることができます。主に地震や津波、飢饉、戦乱などで多くの人の命が失われた場所を中心に塔が建てられました。
供養の象徴!供養塔と一般的な墓の違い
亡くなった人の冥福を祈るために建てられるという点では、両者に違いはありません。しかし、大きな違いもあります。一番の違いは被葬者(葬られている人)の違いです。一般的なお墓の場合、○○家の墓のように、家族単位で先祖の遺骨を合祀して追悼します。
あくまでも家族のための墓であり、家族と無関係の人物が一緒に葬られることはありません。一方、供養塔は特定の人物のためのものではなく、不特定多数の人物を弔うために建てられます。寺院や墓地の一角に建てられている塔には、血縁関係の有無にかかわらず、多くの人が祀られています。
天災や戦乱で多くの人が亡くなった場合などに、その魂を鎮めるために塔が建てられます。たとえば、宮城県名取市には東日本大震災慰霊碑が建立されていて、震災の犠牲となった960名の名前が記されています。近年は、永代供養塔を建立するケースが増えています。永代供養塔とは、寺院や霊園が多くの人の永代供養を行う合祀墓の象徴として建立される塔のことです。
供養塔ってどんなもの?意味と形状の違い
塔の形式は仏教の宗派などにより、意味と形状が異なります。代表的な5つの形式について紹介します。主な供養塔は以下のとおりです。
・無縫塔(むほうとう)
・宝篋印塔(ほうきょういんとう)
・石塔婆(いしとうば)
・五輪塔(ごりんとう)
・多宝塔(たほうとう)
無縫塔は、卵型の形をしていることから卵塔ともよばれます。無縫塔の名は、卵部分がひとつの石だけで構成され、縫い目(継ぎ目)がないことに由来します。無縫塔は鎌倉時代に中国(宋)から禅宗とともに日本に伝来したもので、高僧の墓などに用いられました。京都の泉涌寺を開山した俊芿(しゅんじょう)の墓や鎌倉時代に建長寺を建てた蘭渓道隆の墓が代表とされます。
江戸幕府3代将軍徳川家光の乳母として、徳川政権安定の基礎を築いた春日局の墓もこのタイプです。宝篋印塔は中国の五代十国時代に原型が作られました。日本では、菅原道真や平将門などが活躍していた平安時代中期のころです。本格的に日本で宝篋印塔が建てられたのは鎌倉時代に入ってからです。
正方形に近い土台の上に建てられた塔で、先端部分に棒状の相輪とよばれる部分があります。相輪の最先端には宝珠が乗せられています。死者を弔う追善や自らの罪滅ぼし、延命を願って建てられたといいます。このタイプは僧侶だけではなく、個人のためのものとしても多数建立されました。石塔婆は、鎌倉時代から室町時代にかけて、関東を中心に作られたものです。正式には板石塔婆(いたいしとうば)といいます。
板碑の名称でも知られています。石塔婆の語源はサンスクリット語のストゥーパで、卒塔婆の語源と同じです。ストゥーパは釈迦が亡くなった後に、遺骨(仏舎利)を収めた墓のことをいいますが、釈迦の死後にはインド各地にストゥーパが建立されました。石塔婆は板の形に加工した石材の頭の部分を三角形とし、反対側は地面に刺しやすいよう尖った形状としています。
石塔婆には追悼される人の名前や供養年月日などが刻まれています。五輪塔は平安時代から建立されてきたタイプですが、インドや中国、朝鮮には存在しないもので、平安時代末期に日本で考案された可能性が高いとされます。五輪とは、地・水・水・風・空のことで、仏教では宇宙(全世界)を構成する要素と考えられています。
五輪は、下から四角(地)・丸(水)・三角(火)・半丸(風)・先端が尖った丸(空)の5つの石で構成されています。平安時代に高野聖が行った勧進の影響で世に広まったとする説があります。代表は、神戸市兵庫区の真光寺にある鎌倉時代に時宗を開いた一遍上人の墓です。
五輪塔に刻まれる文字は宗派ごとで異なり、真言宗では梵字を、天台宗や日蓮宗では妙法蓮華経と記すことが多いようです。多宝塔とは、多宝如来や釈迦如来を祀るための塔のこととされます。
寺院建築の一形式として知られていて、日本では、上層階が円形で、下層階が方形の二重塔として建てられています。木造建築以外のものとして、室内に安置される金属製の多宝塔や屋外に置かれる石造の多宝塔があり、石造の場合、屋根がひとつの一重の宝塔が多く存在しています。
供養塔って必要?供養塔の購入にかかる費用の相場
一般の墓と異なっていることや、複数の形が存在していることがわかりました。多くの人を合祀する際に用いられることが多いものですが、個人で建てる必要はあるのでしょうか。必要となるケースを4つ紹介します。
・永代供養する場合
・先祖の追善をしたい場合
・墓をまとめたい場合
・本家・分家に分かれている場合
最初の永代供養については、のちほどまとめて解説します。先祖の追善として建てるのは、現存している墓が傷んでいるケースです。いかに石造りの墓であっても、長い歳月を経ると風雨によって表面が削られ、名前が読めなくなります。そうした古い墓の先祖を供養するため、新たに塔を建てるケースがあるのです。
先祖の墓が複数の場所に分散している場合、供養塔を建てて合祀できます。劣化してしまった個々の墓を修理するのは大変なので、ひとつにまとめて管理しやすくします。また、一族の墓が本家・分家に分かれているときは、供養塔を建立して合祀するケースがあります。
戦前は、現在よりも家の制度がしっかりしていたため、同じ一族でも先祖供養をおこなう本家と、それ以外の分家に分かれていました。当時の考え方に従えば、分家は墓をもたないのが一般的で、その代わりに塔を建てることが多かったようです。次に、購入の費用について考えてみましょう。相場は、タイプによって異なります。最も数多く用いられる五輪塔であれば、数十万円程度で建立できます。
しかし、装飾が多い宝篋印塔や多宝塔はそれ以上の費用がかかります。金額は取り扱う業者によっても異なりますので、直接問い合わせたほうがよいでしょう。
故人への祈りの場!供養塔は永代供養におすすめ
近年増加しているのが永代供養です。先ほども述べたように、永代供養塔とは寺院や霊園が多くの人の永代供養を行う、合祀墓の象徴として建立される塔のことです。永代供養は、寺院や霊園が家族に代わって個人を追善することです。永代供養が増えている背景にはライフスタイルの変化があります。
かつて、墓は家族単位で管理され、先祖代々引き継がれてきました。しかし、高度経済成長期以後の日本では、都市への人口の集中と地方の過疎化が進みました。そのため、過疎化した地方には墓を管理する家族が居住していないという事態が増加しています。
墓は地方にあるものの、自分自身は都市に住んでいるため、年に数回しか墓参りができないケースや、墓を引き継ぐ子どもがいないケース、子どもはいても、親が負担をかけたくないと考えているケースなどがあります。地方に残っている人も高齢化が進み、墓の管理がままならないケースが出はじめています。墓について子や孫に負担をかけたくないと考えている人のなかには、墓じまいを検討する人もいます。
墓じまいとは、墓石を撤去して墓を更地にし、寺院や霊園に使用権を返還することです。墓じまいで問題となるのが、遺骨の改葬先です。改葬とは、すでに埋葬した遺骨を、改めて別の場所に葬ることです。改葬先として想定されるのが以下の5つです。
・一般の墓
・使用年数が限られた墓地
・海洋散骨
・自宅
・永代供養
一般の墓に葬るケースとしては、地方にある墓を墓じまいして、現在家族が住む地域に墓を移転する場合です。使用年数が限られた墓地とは、定められた期間内だけ利用できる墓で、期限がくると更新するか墓を返還するか選ばなければなりません。海洋散骨とは、粉末になった遺骨を海にまくことです。
自宅で弔う場合は、自宅のなかの仏壇などに遺骨を安置して追悼します。永代供養とは、寺院や霊園が管理する施設で故人を供養することです。永代供養には合祀墓・合葬墓、樹木葬、納骨堂などの形式があります。活用するメリットは、墓の維持にかかる経済的負担を減らせることや、子孫に墓地を維持する負担をかけずに済むこと、墓参りがしやすくなることなどがあります。
寺院や霊園によっては、宗派を問わず利用できるという点でも注目されています。永代供養塔は、故人を偲ぶための祈りの場となりますので、永代供養をしたからといって故人とつながりが切れてしまうわけではありません。ただし、一度永代供養を選択してしまうと遺骨を取り出すことは不可能となるので、その点については注意が必要です。
まとめ
今回は供養塔の意味や供養塔の形式、特徴、永代供養を利用するメリットについて解説してきました。時代の移り変わりとともに、ライフスタイルや家族の在り方は大きく変化しました。こうした変化があるため、先祖代々の墓を一族で守るという従来のスタイルが難しくなっているのは否めません。少子高齢化が進むなか、これまで地方の墓を維持してきた人たちも高齢化が進み、自分たちだけでは墓を維持するのが難しくなっています。今後は、一族ごとで墓を守るというスタイルから、合祀・合葬墓で永代供養され、永代供養塔で祈りをささげるスタイルに変化していくのかもしれません。
-
 引用元:http://www.hasunokai.jp/
引用元:http://www.hasunokai.jp/
持明院「はすの会」
| キャプチャ |  |  | 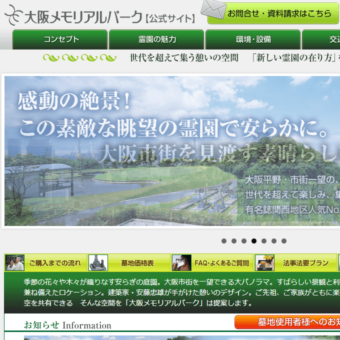 |  |  |
| 会社名 | 持明院「はすの会」 | 一心寺 | 大阪メモリアルパーク | 霊園墓石のヤシロ | 海泉寺 |
| 強み | お寺による管理で信仰心に基づいた厳粛な供養が期待できる | 大阪市の無形民俗文化財にも指定され、年中無休で参拝可能 | 大阪市街を一望できる大パノラマなど美しい景観と利便性を兼ね備えている | 大阪府及び兵庫県を中心に関西地方において葬送トータルサービスを提供 | 永代供養を中心として従来型の屋外墓地や海洋散骨にも対応 |
| 詳細リンク | |||||
| 公式リンク | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら |
おすすめの永代供養寺院・霊園5選!
| 商品画像 |  |  | 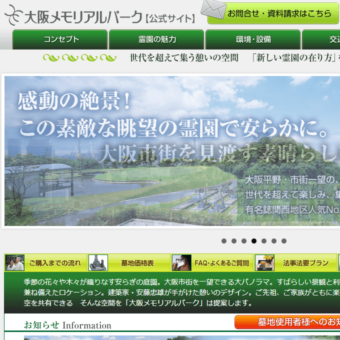 |  |  |
| 商品名 | 持明院「はすの会」 高野山の納骨と永代供養墓 | 一心寺 | 大阪メモリアルパーク | 霊園墓石のヤシロ | 海泉寺 |
| 特徴 | どんな人でも永久に供養。持明院での永代供養を実施。冬場に雪が降っても交通機関は麻痺しません。冬の高野山を満喫してく ださい。 | 納骨、おせがき、千躰仏、断酒祈願等、独自の仏事を実施。 | 生駒山の自然と地形を生かした、美しい景観の霊園。 | 関西エリアにて、明確な葬送トータルサービスを提供。 | 丁寧な永代供養を行う、地域に根付いた歴史ある寺院。 |
| 公式サイト | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら |
| 詳細リンク | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら |