永代供養にお布施は必要?

仏教式で葬儀・法要などを行うとき、ご僧侶をお呼びすることになります。お墓においても納骨法要の際には、ほとんどの遺族がご僧侶にお願いして読経していただくものです。
永代供養を契約した場合でも、法要などの際にはお布施の必要は生じるんでしょうか? ここでは永代供養とお布施をテーマに述べたいと思います。
お布施って、そもそも何?
永代供養とお布施について書く前に「お布施」についてご説明させていただきます。本来の意味や、そもそもの在り方を知ることで、お布施に対する気持ちが変わってくるからです。
■悟りに至るための「6つの徳目」のひとつ
そもそも、お布施とは、大乗仏教で悟りに至るため、6つの徳目『六波羅蜜』のひとつです。『布施波羅蜜』と言って「檀那=分け与えること」他者に施すことを指します。布施の修行には3つの形がありますが『財施』にあたるのがお布施です。
■お礼や対価ではない
起源をお読みいただいておわかりとは思いますが、そもそもが「行」なので「させていただくこと」。仏さまに捧げる修行のひとつですので、お布施もご本尊に捧げるためのものです。ともするとお礼や対価といてご僧侶・お寺に差し上げるものと勘違いしてしまいがちなので、注意しましょう。
■金額のめやすはあるか?
結論から言えばありません。上記のとおり、大切なのはご本尊に「お捧げする」という「気持ち」です。ご僧侶としても経済的に余裕のないご家庭から多くのお布施をいただこうなどとは思っておられないもの。
しかし、どうしてもということであれば、お通夜・お葬式で関西であれば20万円前後、納骨式・四十九日・一周忌であれば3万円~5万円ほど。それ以降の年忌法要では1万円~5万円が相場と考えて良いと思います。
前述のとおり、無理をして支払ってあとで経済的に困窮してしまうようなことがあってはいけないので、ご僧侶に正直にお話しした上で、できる範囲ですることをおすすめします。とにかく「気持ちが大切」であることを忘れないでください。
永代供養でも、お布施は必要?
永代供養とは、お墓の管理と供養の一切を、運営する業者や寺院が代行してくれるサービスを指します。ですから、遺族は供養をする義務はありません。
しかし、仏教には『追善供養』という考え方があり「遺族が供養することで故人が極楽浄土に到達することを後押しできる」ということになるため、遺族が供養をするというのはたいへん良いこととされています。
そして、永代供養においても、故人の遺骨をお墓に納骨する際は、ご僧侶に読経していただくことになるのが通常です。しかし、ほとんどの永代供養契約では、あらかじめ支払う金額にこの費用がすでに含まれています。
契約前には「納骨時のお布施は含まれていますか? 」と確認することでより安心でしょう。そして四十九日の法要は、親族が遠方に多い遺族の場合、繰り上げ法要することもありますが、一般的には納骨法要といっしょに行われるため、お布施は別個に用意することはありません。
一周忌、三周忌などは重視されますが、そのあとは簡略化されることが多く、遺族だけで済ませる家庭も多いでしょう。しかし、時にはご僧侶をお呼びして読経していただくのも良いのではないかと思います。
お布施のわたし方
永代供養でも回忌法要では「お布施は必要」ということをおわかりいただいたところで、その渡し方についてもご説明しましょう。
■おわたしするタイミング
お布施は法要がはじまる前、ご僧侶にごあいさつするときにおわたしするのがスマートでしょう。「本日は○○の○回忌ですが、何卒よろしくお願い申し上げます」と言いながらおわたしするとていねいな印象です。
■お布施袋がある
お香典袋は不幸があった遺族におわたしするには良いですが、ご僧侶は不幸があったのではありませんから、専用のお布施袋か、白封筒に「御布施」と書いたものに入れておわたしします。
■おわたしのときは「お盆」か「袱紗」
お布施は袱紗(ふくさ)に包んでおき、そこから取り出す、もしくは「祝儀盆」と言う黒いお盆お盆にのせておわたしするのが礼儀です。もし用意できないときは葬儀社などに相談してみましょう。
■お盆・袱紗のマナー
祝儀盆でのおわたしの場合、お盆にのせたままおわたしします。袱紗から取り出しておわたしする場合には、取り出してから袱紗の上にのせた状態でおわたしします。
「袱紗から取り出して袱紗にのせる」というのは、意外にわからないところですよね。知っておけばおわたしするときに不安を済むことでしょう。
まとめ
「永代供養にお布施は必要か? 」について書かせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。お布施の由来を知ることで、おわたしするときの意識も変わってきますよね。
また「永代供養なのに遺族も供養したら二重に供養することになってしまうけど」と心配している方には「遺族の供養は追善供養となる」ので、だいじょうぶです。むしろ「永代供養だから何もしなくて良い」のですが、それだと故人を偲んだり、向かい合う機会が失われがちなので、区切りには遺族が法要を執り行うのは良いことでしょう。
法要を執り行わないまでも、遺族で永代供養墓に集まって墓参するなど、遺族として供養する機会を設けるだけでも良いですね。出かけられない事情があれば、遺族そろってお宅で手を合わせるだけでも心は伝わるので、おすすめさせていただきます。
-
 引用元:http://www.hasunokai.jp/
引用元:http://www.hasunokai.jp/
持明院「はすの会」
| キャプチャ |  |  | 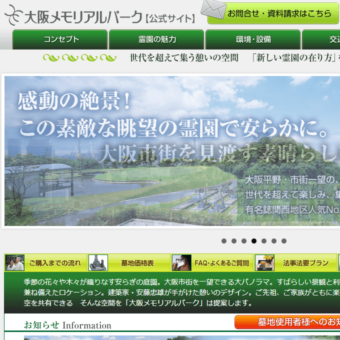 |  |  |
| 会社名 | 持明院「はすの会」 | 一心寺 | 大阪メモリアルパーク | 霊園墓石のヤシロ | 海泉寺 |
| 強み | お寺による管理で信仰心に基づいた厳粛な供養が期待できる | 大阪市の無形民俗文化財にも指定され、年中無休で参拝可能 | 大阪市街を一望できる大パノラマなど美しい景観と利便性を兼ね備えている | 大阪府及び兵庫県を中心に関西地方において葬送トータルサービスを提供 | 永代供養を中心として従来型の屋外墓地や海洋散骨にも対応 |
| 詳細リンク | |||||
| 公式リンク | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら |
おすすめの永代供養寺院・霊園5選!
| 商品画像 |  |  | 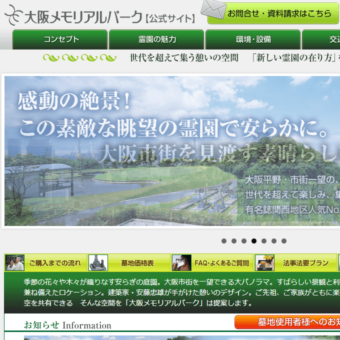 |  |  |
| 商品名 | 持明院「はすの会」 高野山の納骨と永代供養墓 | 一心寺 | 大阪メモリアルパーク | 霊園墓石のヤシロ | 海泉寺 |
| 特徴 | どんな人でも永久に供養。持明院での永代供養を実施。冬場に雪が降っても交通機関は麻痺しません。冬の高野山を満喫してく ださい。 | 納骨、おせがき、千躰仏、断酒祈願等、独自の仏事を実施。 | 生駒山の自然と地形を生かした、美しい景観の霊園。 | 関西エリアにて、明確な葬送トータルサービスを提供。 | 丁寧な永代供養を行う、地域に根付いた歴史ある寺院。 |
| 公式サイト | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら |
| 詳細リンク | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら |




